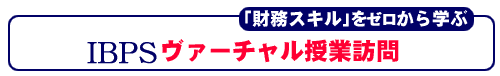
|
とある土曜日の午後1時半、講義が始まった。教室内には30代前半とおぼしき受講生が多いが、50代の男性も、少ないながら女性もいた。人数は20人弱。
|
|

|
手元の資料には、新聞に掲載された決算公告のコピーが10種類。 その中に、「ワールド」、「いなげや」、「松坂屋」のものがあるという。どれがその企業の決算公告なのか当てるのだ。 3社はそれぞれ衣料品メーカー、スーパー、百貨店であり、各業態には特徴がある。たとえば衣料品の粗利率は40%を超えることが普通だそうで、それを知っていれば、どの決算公告が「ワールド」のものか、大体の見当がつくとのこと。 「なるほどなぁ」という気持ちで聞いていると、千賀先生はコピーを配り始めた。日経新聞の記事だ。「アパレル業界地図に異変」という見出しが踊っている。記事にはところどころにラインが引かれ、そこから引き出し線で「SPAとは」や「シーズン前の見込み生産の抑制」「自社ブランド開発力」などという手書きの文字が記されている。 |
|
すると、話は「ユニクロ」の店舗を急増させている服飾製造小売企業「ファーストリテイリング」に移った。同社はもともと高い粗利率を、1年半で8ポイントも上げたのだという。
|
|
むろん学んだのはアパレル業界の異変だけではない。有価証券報告書や決算短信、貸借対照表の話と続き、今までぼんやりとしかわかっていなかったことが徐々に明瞭になってくるのを感じた。例えば損益計算書。「売上総利益」「営業利益」といった言葉の意味が明確にわかるようになってきたのだ。実にうれしいことだ。 そもそもこの講座は、ビジネスに関わる数字のことをよく知らない人たちが対象。まさに私などはぴったりなのである。だから千賀先生は、話題が変わり一とおり説明を終えるたびに新聞のコピーを配る。つまり鮮度の高い素材を使って、受講生自身に関連づけて考えさせるわけだ。そのうえ受講生のほぼ全員が指名され、質問に答えていた。当事者意識を持たせようという千賀先生の熱意がダイレクトに伝わってくる。 |
|
しかも新しい知識を得た上で関連する記事を読むのだから、今までほとんど理解不能だった記事がはっきりとわかってくるし、おもしろくなってくる。単なる「お勉強」では退屈してしまうが、ナマの情報を自分に関連づけて考えれば、苦手な数字の話も「我が身に降りかかる問題」として考えることができる。忘れないし、考え方にも影響を及ぼすはずだ。事実、1時間半ぶっ続けの講義の間、受講生全員が真剣な表情で聞き入っていた。
|
1時間半ぶっ続けの講義の後、10分ほどの休憩を挟んで始まった後半は、「会計ビッグバンの要点」がテーマ。会計ビッグバンがビジネスの世界に大きな影響を及ぼすことは何となく知っていたが、具体的にどのような影響が出るのかまでは知らない。会計ビッグバンは連結ベースへの移行が話題になっているが、それがどういう意味を持つものなのか。
詳しくは知らない者に共通したこの疑問に、千賀先生は明快に答える。一言でいえば、連結ベースになることで個別企業よりも企業グループ全体の財務状況がよく見えるようになる――ということ。 パワーポイントを活用しビジュアルを用いた説明は、数字オンチの人間にとっても非常にわかりやすい。
また、今回の講義でも、第一回で詳しく学んだ損益計算書の参照を繰り返し求められたことで、損益計算書を具体的な事例にあてはめて考えることができた。
前回と今回の受講で何度も復習することで、損益計算書の見方だけでなく、その活用法の一端に触れることができたように思う。これは大きな収穫だ。
短時間でこれだけの収穫を得ることができたのは、正直いって予想外。思っていた以上に実践的かつ効率的に学ぶことができたと思う。「成果を出せる人材育成」は、ダテではなかったのだ。今回のIBPS潜入取材はその一部を垣間見たに過ぎない。少なくとも経営に関わる基本的な数字や言葉については、はっきりと理解することができた。この結果、それらに対する苦手意識をかなり払拭できたわけで、これこそが最大の収穫なのだと思う。
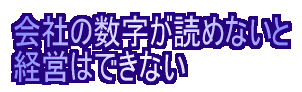

|

